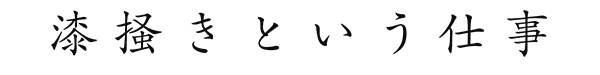

かねてから手仕事に興味があったこともあり、東北で受け継がれている多くの伝統工芸を訪ねてきた。それらの経験を踏まえてみても、「漆掻き」という仕事は実に不思議だ。
もちろん、漆掻きは、漆芸に必要な素材を採る仕事であって、最終的な完成品を目指す他の工芸とは異なる。
とは言え、刃物だけで一切の機械を使わず、技術と感覚だけで漆を掻き採っていくこの仕事は、他の手仕事と比べてみても手仕事の極みと言えるだろう。
手仕事としてみた漆掻きの最大の特徴は、生きたウルシの木を相手にしている点である。木工芸に携わる職人たちは、素材となる木材を「木は生きているから」と語り、加工の難しさを口にするが、漆掻きは、呼吸し成長しようとする文字どおり生命を持つ木を相手としている。漆掻きという仕事の難しさも面白さもここに尽きる。
漆掻きは、初夏、芽吹きが落ち着いた頃から始まる。
職人はカンナと呼ばれる専用の刃物を持ってウルシの林に行き、ウルシの幹にわずか数センチの「辺」(切り傷)を付ける。これが「目立て」と呼ばれるもので、これが「これから辺を付けていくぞ」という職人からウルシの木へのメッセージとなる。その後は、約4日から1週間という間隔で2辺、3辺と徐々に長い「辺」を付けていき、滲み出てくる漆を専用のヘラで掻き採っていく。採った漆は季節によって塗りの際の硬化速度や透け具合などの性質が異なるため、初夏の初漆、盛夏の盛漆、晩夏の末漆などと区別される。そして、秋を迎え、葉を落とす頃になると、職人は「裏目掻き」と呼ばれる、幹を一周するほどの長い辺を付けて一年のシーズンを終える。


漆掻きを極限まで簡単に説明すると以上のようなこととなる。つまり、初夏から秋までの時間のなかで、ウルシの幹に徐々に大きな傷を付けていき、漆を採るというものだ。実際、漆掻きの現場では、この作業が延々と続けられる。
一人前の漆掻き職人がひと夏に掻くウルシの木は約400本。まさに地道そのものといった作業が続く。
漆掻きという仕事の不思議さは、一見すると単調極まりない作業のなかに、見えない技術や感覚が膨大に込められているということだ。
その証拠が、職人たちが採った漆は、ひとつとして同じ品質なものがないという事実だ。樹齢、生育地、日当たり、葉の繁り具合など、ウルシの木は生き物だけあって一本一本異なる。人の顔がすべて異なるように漆の質もそれぞれの木で違うのだ。これに加え、漆を採取する職人の技術や感覚で滲み出す漆の量はもちろん、漆の質も変化する。あの職人の漆は硬い、柔らかい、透け具合が良い悪いなど、職人ごとに大きく異なる漆の顔が存在する。興味深いのは、こうした明らかな差異を生む原因の中身がはっきりしていない点だ。
漆掻き職人は独立すれば基本的には一人で山に入り、漆を掻き採る。基本的な技術はあれど、ウルシの木と向かう日々のなかで技術を研鑽し、独自のスタイルを築き上げていく。そのため、職人ごとの独自の漆掻き技術と哲学を持つ。
しかし、これらは同じ土俵で比較されることがないため、差異を生む原因として明らかにされないのだ。
また、職人たち自身も、自らの技術の詳細を言語化することはない。日々の膨大な繰り返し作業から得た技術は、文字どおり肉体の言語であり、実に繊細な身体感覚が支えている。しかも、この肉体の言葉は、自然のめまぐるしい変化のなかで常に移ろい、固定化されることはない。結局のところ、「漆掻き」という技を言語化するのがそもそも無理なことと言えるかもしれない。


さて、鈴木健司である。彼もまた、身体感覚をフルに使って漆を掻き採る職人の一人だ。
透けが良く、かちっと艶やかに固まる理想の漆を求めて山に入る鈴木健司の仕事ぶりは見ていて気持ちがいい。
大柄でありながらも柔軟性を持った身体をすっすと動かしながら恐ろしく切れるカマで樹皮を削り、次の瞬間には、しゅっと迷うことなくカンナを幹にすべらせている。
走ったカンナからは茶色の外皮と白い内皮が帯状になってそれぞれに分かれながらするりと伸び出てポロリと落ち、鮮やかな白い線にも見える辺が幹に現れる。そして、鈴木健司の手がさっとカンナを裏返し、メサシと呼ばれる薄い刃で辺をさっとなでると、漆がジワリと滲み出してきて、辺を伝って流れ出す。それをヘラでさっと掻き採り、逆の手で持ったタカッポと呼ばれる容器にストンと落とす。一瞬芸にしてまったく無駄のない動きだ。
「日々、どうやって漆が良く出る木に育てるかを考えている」と言うが、それはあくまで初夏から秋までかけて段階的にウルシの木に辺を付けていくプロセスの進め方で、森の中では、「カンナを幹に入れた瞬間に伝わる感覚で動いている。木から伝わってくる何かがある」と鈴木健司はいつも言う。
写真を撮るだけでは、鈴木健司の言う「何か」というものはよくわからない。しかし、鈴木健司が迷うことなくカンナを走らせ、幹に刻んだ辺から滲み出る漆の艶やかな光を見ていると、きっとウルシの木の生命に関わることだろうと確信している。
いつだったか、夏の暑い森の中で鈴木健司が言った言葉がある。「木にとって漆は、俺たちの血液と一緒。生々しくて、熱もある。だから気持ちに届いてくる」。
漆を掻くことを生業にした鈴木健司の眼差しは、ウルシの木の深いところを見つめている。


