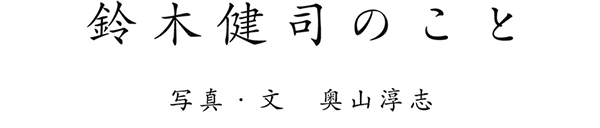

岩手県二戸市の浄法寺という小さな山里に鈴木健司という男が暮らしている。
彼と初めて出会ったのはもう10年近く前のこと。ある単行本制作の撮影で彼の仕事場であるウルシの林を訪ねたのが始まりだ。
雫石から車を走らせ、僕が到着したとき、鈴木健司は、すでにセミが鳴く林の中で汗を流していた。
そして、僕が撮影の意図を話した後の鈴木健司の開口一番が、「俺なんて撮影して大丈夫なの?」だった。続けて「今みたいな梅雨時期はさ、暑くて嫌になちゃうんだよね。帰りたいよ。もう」と少し憮然とした顔付きで煙草をくわえた。
正直、僕にそんなことを言われても困ると思ったが、鈴木健司はこちらの気持ちを知ってか知らずか、美味そうに煙草を吸っていた。
そんな彼が腰を上げたのは、煙草を数本吸って、なぜかシャツを脱いで上半身裸になると、林の脇を流れる水路でバシャバシャと水浴びをするためだった。いくら自然が豊かな岩手とはいえ、湧き水でも何でもない水路で水浴びをする人に出会ったことがなかったので少し呆気にとられたが、鈴木健司はさも当たり前のように身体にしたたる水滴を手ぬぐいで拭い、シャツを羽織ると漆掻きの道具を手に林の中に入っていった。
こうして始まった鈴木健司の漆を追う撮影は気がつけば何年にもわたり、数年前には初夏から秋まで密着してその仕事ぶりを記録するなど、僕にとっても大きなものに成長していった。

鈴木健司の仕事は、ウルシの木から漆を採ることと、採った漆を使って漆器を作ることだ。国産漆の最大の産地として知られる浄法寺で、漆掻き職人と塗師という二つの場を行き来し、“鈴木健司の漆”という世界を深めている。
その仕事ぶりは、初めての出会いで見せた表情のように何のてらいもない。仕事の辛さや難しさは簡単に口にするし、さぼり癖がないわけでもない。もちろん、信念や哲学めいたもので自らを大げさに飾る気などさらさらない。
それでも、僕から見ると、鈴木健司の漆の世界は不思議な魅力を放っている。なぜだろうと考えてみると、鈴木健司という人間の芯の強さに繋がっていく。
そのことを伝えるエピソードのひとつは、福島県の会津出身の彼がこの浄法寺にやってきた理由だろうか。
実は、鈴木健司の実家は、会津漆器の製造メーカーだった。一時は跡取りとして父とともに会社運営に携わったこともあったが、経営者の道を捨てて浄法寺にやってきた。その理由は「本物の漆器を作っていきたいから」という鈴木健司の情熱からだった。
当時、鈴木健司の父親が経営する会社は、機械化された、いわゆる大量生産の漆器製造を主としていた。一方の鈴木健司が求めたのは、会津漆器の伝統に根ざしたもの。会社の方針をめぐり、父との間で確執が生まれたのは当然のことだった。結果として鈴木健司は会社を去るのだが、次に向かった先は、会津漆器の伝統的な技法を教える会津漆器技術後継者養成所だった。彼は経営者ではなく一職人として会津漆器に関わっていこうとしたのだ。そして、養成所で塗りを学ぶなかで出会ったのが自ら採った漆で漆器制作を行う故・谷口吏(たにぐち つとむ)氏。独自のスタイルを貫く氏の仕事ぶりに「漆」の本質を見出した鈴木健司の行動は、弟子として願い出ることだった。


こうして、谷口氏の下で漆掻きと漆塗りを両輪で行う今のスタイルを学び始めた鈴木健司だったが、再び訪れた転機が浄法寺に行くということだった。漆掻きという仕事に深い興味を持つようになった鈴木健司に谷口氏は、「本当の漆掻きを学ぶなら、岩手の浄法寺に行け」と伝えたのだ。
2005年、この言葉に素直に従った鈴木健司は、日本うるし掻き技術保存会が実施する漆掻き職人研修制度を利用し、浄法寺で本格的な漆掻き職人としてのキャリアをスタートさせたのである。
以来、10年以上にわたり、鈴木健司は初夏から秋の間は漆を求めて山々を巡り、同時に自らで採った漆を塗って漆器を制作するという活動を地道に続けてきた。
漆に関わる仕事を行う職人は全国に数多く存在するが、漆掻き職人と塗師を生業とする者は数えるばかりだ。鈴木健司は谷口氏に続く、漆掻きと塗師という二足のわらじを履くパイオニア的存在として歩んできたのだ。「地道」なんて言葉はどうも鈴木健司には似合わないような気もするが、実は最もふさわしい称号なのかもしれない。
鈴木健司はこう見えて、案外強い。鈴木健司はああ見えて実は努力家だ。鈴木健司はあんなことを言うが、本当は漆の仕事を愛している。
それが透けて見えるようになったのは、繰り返し彼の仕事場にカメラを向け、彼の姿と言葉を拾った先のことだった。

